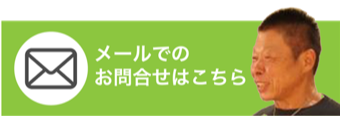壁画についてのよくある質問
もちろんトリック壁画は描きます。
弊社の会社設立(1993年)した当時は、トリックアート美術館が日本にできはじめた時期でしたので、弊社でもその頃数多くのトリック壁画を制作しました。
その後ブームは静まりましたが、その後もブームとは関係なくトリックを使った壁画技法は普段の壁画の中に自然に取り入れています。
弊社がトリックを壁画に取り入れる目的は大きく二つあります。
(1)トイレなどの狭い空間を広く見せたり、窓のない閉ざされた部屋を開放感を出すなど、建物の欠点を目の錯覚を利用して解決する。
(2)絵を見ながら人が動くと、絵の人物の目がついてきたり、物が動いて見えるなど、見る人をビックリさせる遊び心で話題と親近感を提供する。
もちろん、両者を組み合わせる場合もあります。
ただの何もない壁に、ドアやエレベーターを描いたり、隣の部屋を描いたり・・・・。
単なるブームとしてのトリック壁画ではなく、トリック壁画の持つ特性と利用目的を理解した上で活用していただければ、活躍の場はまだまだ無限に広がると思います。
プールの場合、地上部の壁面と水に漬かっている壁面や底面があります。どちらも、壁画は描けます。実際に施工例(下の写真)もあります。

ただ、常に水に漬かっている場所は条件が大変過酷です。水による塗装面の剥離とカルキによる害です。
塗料は、プール専用塗料(プールコート)を使います。ただ、耐久性は万全ではありません。シーズンオフは水を抜いて、できるだけ乾燥させておくことをおすすめします。
幼稚園の場合はプール画の需要は多いと思います。水恐怖症の子供には、てきめんの効果が期待できます。無機的で不気味なコンクリート面と青くて冷たいイメージの水。筆者自信、子供時代に水(プール)恐怖症でしたので、その心理がわかります。
しかし、プールの底にかわいい動物などの絵が描いてあったらどうでしょう。プール自体の色もピンクやイエローなどの暖色だったら、恐怖の心理は和らぐと思います。
現在、プールについては特殊な施工方法を研究中です。耐久性に不安のある塗装という方法ではなく、セラミック板に絵を描いて焼成処理をするという画期的な方法です。
プールが楽しいイメージに大変身して、子供たちから水(プール)恐怖症がなくなるようにプール画が広がっていくことを期待しています。
ときどきブロック塀に描かれた壁画を見かけますが、残念ながら下地処理が不完全なため虫が食ったように剥がれているのが目につきます。
まず、塗膜は裏からの浸水に弱いため、巣穴を完全に埋める必要があります。また、コンクリートに含まれるアルカリ成分が塗膜を冒すため、完全に密封する必要があります。
下地調整塗材としては、ポリマーセメント系下地材(例:SK化研「ミラクファンドKC-1000)をローラー(中毛)で2回塗り、その後水性サーフェイサー(例:SK化研「水性ソフトサーフSG」)をローラー(中毛)で2度塗りしてください。もちろん、下地調整塗材を塗る前に、ケレンや水洗いで苔、カビその他の付着物をきれいに取りのぞいてください。
下地調整がすんだら上塗り用の塗料で壁画の制作にかかって結構なのですが、下地調整塗材は上塗りが塗布されないと、地のままでは耐候性がありませんので、念のため白の上塗り塗料を2度塗ってから描画作業に入ることをおすすめします。
建築物や洞窟などの壁面に描かれた絵画のこと。絵画は、元々壁画から始まった。一種の装飾の目的が目的であったが、寺院、神殿、墳墓などでは宗教的な意味でも使われた。絵画は、次第に建物や洞窟から離れ、板や布に描かれるようになり独立した存在となっていった。
しかし、壁画は多くの人が同時に見ることができたり、空間全体を絵画空間に変容させて見る人を包み込む効果があり、その空間の意味を変えたり、人を感動させるエンターテインメントな空間づくりに活用されるようになり、今でも数多く制作されている。
板や布に描かれた一般的な絵画が平面的な作品であるのに対し、壁画は空間アート的な要素が強く、その壁画的な効果がさまざまな所で注目され、活用されはじめている。
基本的に、水と空気以外であればほとんどの下地に壁画を描くことができます。ただし、下地の素材と塗料の種類の間には相性のいいものとそうでないものがありますので十分な注意が必要です。
大別すると、下地に塗料が密着しないケースと素材や使用する塗料が旧塗膜を冒してしまうケースです。特に、アルミやガラス、塩ビフィルムなどには特別な下地処理が必要です。木材、モルタル、鉄などの一般的な壁材の場合も、木材にはヤニ止め、モルタルにはアルカリ止め、鉄にはサビ止めなどの下地処理を怠るとトラブルになります。
下地との相性については、塗料メーカーにいちいち確認するのが一番です。ちなみに弊社では、簡易的な密着テストを行ったり、事前に実験を行うようにしています。
壁画を描く壁の下地にあわせて水性、油性、溶剤系の塗料を使い分けます。例えばブロック塀やコンクリート壁には水性塗料、シャッターやトタンには油性やウレタン塗料を使います。その他に、耐候性、物件の特性、作業環境、作風によっても使い分けています。最も多く使用するのは、水性アクリル塗料です。
当社では、より環境にやさしく安全な水性塗料に移行するよう努力しています。
弊社では、商業施設から公共施設、一般住宅に至るまで幅広い物件を手がけています。具体的には、店舗、幼稚園・保育園、老人ホーム、病院、遊園地、プール、地下道、工事現場、ガス・水道タンクなどからアパート、個人住宅などさまざまです。中でも多いのは、飲食店と幼稚園・保育園です。
壁画以外にも、天井画、床壁画、ブロック塀壁画、シャッター壁画、プール壁画などさまざまな場所に描いています。
地域的には、関東一円です。特に地元・春日部市では、「壁画のある街づくり」を推進しており、数多くの壁画が集中しています。
ただ描きたいものを描くのではなく、その場所のイメージや目的に合っているかを検討することが大切です。
例えば人通りの少ない場所に人物画を描いたら、夜間、おばけ騒動になってしまった、という例があります。いくら上手く描けていてもこれでは逆効果ですよね。
壁画デザイン上の主な留意点としては、
・図案やタッチが壁画の目的やテーマにそっているか。
・企業イメージや景観的な観点から、色使いが適切か。
・建物や周囲の環境と調和しているか。
などがあります。
もともと壁画のない場所に壁画を描くということは、違和感や不自然さを伴いやすいものです。そこで、建物や周りの環境に馴染ませるために、
・周囲の壁の色とトーンを合わせる。
・周りの建物や景観を借景として活用する。
・建物の障害物を逆利用して、絵の一部に取込む。
などの工夫が大切です。
弊社ではそのようなデザインの提案やアドバイスも行なっておりますので、ご気軽にご相談ください。
壁画制作を依頼する上でよく起こるトラブルは例えば次のような事です。
・技術レベルに関すること。例えば、イメージやクオリティーに関する依頼者と制作者間のギャップ。
・見積り金額に含まれる範囲についての双方の解釈の違い。
上記のようなトラブルが起きないように、次の点に気をつけて依頼しましょう。
・ご希望の壁画のイメージやタッチなどがある場合は、事前に資料を制作者に見せた方が打合せもスムーズです。
・依頼先の機能を確認する。企画・デザイン・制作・施工のどの範囲までを担当してもらえるのか確認しましょう。
・デザイン機能の有無を確認する。版権や著作権保護法にも注意してください。
・相手のイメージやクオリティーを確認する。施工事例の写真・見本やサンプルなど、できるだけ詳細な資料を提供してもらいましょう。相手の作業場など事前に見学しておく事も肝心です。
壁画を描いて落書きがなくなったという例は、うまく成功したケースです。一般に、壁画を描くと確かに落書きが減るという傾向はあるようです。
以下は、弊社の過去の17年間の経験といろいろな実験から出てきた仮説です。
(1)何も描いてない無機質な壁よりも、絵を描いてある壁の方が落書きは少なくなる。
(2)壁の一部に描いた場合よりも、壁全面に描いた方が落書きは少ない。
(絵を描いていない無地の部分に落書きされるケースが多い)
(3)壁画の中には、落書きを逆に誘発する絵がある。絵の内容によって大きく結果は異なる。
(4)どんなにいい内容の壁画を描いても、壁面の汚れや周辺のゴミの掃除などを怠ると落書きを誘発する環境になってしまう。
(5)地下道やトンネルの場合、照明の電球切れや照度不足、照明の色温度によって壁画のイメージが悪くなり、落書きが多くなる。
弊社では長年、壁画制作を専門にしてきましたので、(3)~(5)のことを特に多くの人に知ってもらいたい、特に行政の人に知ってもらいたいと痛感しています。
特に、(3)の壁画の絵の内容については力説したいと思います。
・暗いイメージ、不気味なイメージ、冷たいイメージの絵は避ける。
・暴力的、攻撃的なイメージの絵は避ける。
・汚い色使い、雑然とした絵は避ける。
・一時的な流行りはモチーフにしない。
逆にどんな絵がいいかというと、
・明るくて楽しい絵。
・ほのぼのとして温かい絵。
・見た人が思わずニコッとする遊び心のある絵。
・ファンタジックで夢のある絵。
・元気の出てくる絵。
・ほっとして心が和む絵。
まとめると、どんな時代でも時を超えて人が持っている「和」「楽」「温」「笑」などの普遍的な「平和で幸福な心」に呼びかけるような絵をデザインすること。ちょっと抽象的ですが、弊社では常にこのことばかりを考え、追求しています。人が喜ばない壁画は無益です。それはむしろ「壁画公害」ともなります。
アートは、それ自体が強力なパワーを持っています。表現の方向しだいで「人を幸せな気持ち」にも「暗くすさんだ気持ち」にも人を導きます。壁画を描く前に、これから影響を与える人々や地域のことを真剣に考えることが重要です。
弊社では、これまでありとあらゆる場所に壁画を描いてきました。そのため、実にさまざまな塗料を用途や目的によって使い分けています。
(1)モルタル、木、鉄から土壁などの下地の素材によって
(2)短期・中期・長期用など耐久期間によって
(3)屋内用、屋外用、多湿用、水中用など施工場所によって
(4)耐候性、耐油性、耐摩耗性、防塵性、防汚性、低臭性など求められる条件によって
(5)水性、油性、2液反応型など作業性や作業の環境によって
(6)ツヤ消し、3分ツヤ、5分ツヤ、全ツヤなど仕上がりの風合いによって
(7)速乾性、遅乾性など、作品の仕上げレベルや絵画技法によって
(8)天然材料からつくられた自然塗料など人や環境への配慮によって
その他にも、さまざまな条件を考慮して、適切な塗料の選択を心がけています。新製品についても、いち早くテスト使用を行うなど積極的に取り組んでいます。
まず第一に、壁画の耐候性を増すために、まず太陽の紫外線をカットしなければなりません。UVカット剤入りのフッ素コート(例:ターナー色彩「UVカットフッ素一液クリヤー」)などがあります。水性アクリル塗料などで描かれた壁画の上に溶剤系のクリヤーを塗ると、塗膜を溶かしてしまいますので弱溶剤系(塗料用シンナー)か水性のクリヤー(例:ターナー色彩「水性UVコート」)をお使いください。
第二に、壁画の落書きからの保護です。そのために、落書き除去用のクリヤー(例:東日本塗料「スカイクリヤー」、SK化研「SKハードクリーン」)があります。ただ、使用するには高度な技術を要しますので、プロに任せた方がいいでしょう。
第三に、壁画の汚れ防止です。上記の落書き除去用クリヤー自体汚れがつきにくい効果はありますが、汚染物質を分解除去してきれいに保ちたいなら、光触媒コートがあります。ただ、まだ新しい製品であり、当社でも、立体造形に使用していますが、3年未満の実績しかありませんので、具体的な製品名は差し控えさせていただきます。ただ、この分野の技術の進歩は目まぐるしいものがあり、性能は確実に向上しています。これも、高度な技術を要しますので、施工はプロに任せた方がいいでしょう。
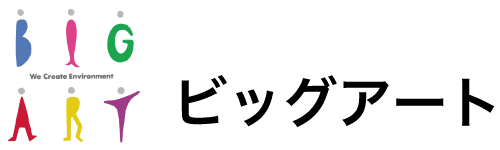 有限会社ビッグアート
有限会社ビッグアート